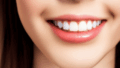芥川龍之介の代表作「羅生門」。この物語を読んだ多くの人が、最後に抱く大きな疑問、それは下人の行方ではないでしょうか。羅生門の下で下人が何を考えていたのか、そして彼の最後の行動が何を意味するのか。
この記事では、羅生門の結末に関する深い考察を行います。下人の行方は誰も知らないという結末がもたらす効果や、その後どうなったストーリーなのかという想像を掻き立てる謎、さらに芥川龍之介の羅生門の最後の一文はなぜ変更されたのか、その理由にも迫ります。
羅生門の下人の行方について、その後の老婆の運命も含めて多角的に考察し、作品の持つ深いメッセージを解き明かしていきます。
この記事を読むと分かること
- 下人が盗人へと変貌するまでの詳細な心理プロセス
- 物語の結末「下人の行方は、誰も知らない。」に込められた作者の意図
- 作品全体に散りばめられた象徴的な表現の解釈
- 「羅生門」という作品が現代の私たちに問いかける普遍的なテーマ
羅生門の下人の行方を考察する上での前提
- 羅生門に現れた下人の境遇は?
- 下人は羅生門の下で何を考えていたのか?
- 羅生門のにきびは何を象徴しているのでしょうか?
- 羅生門で下人が失望したのはなぜ?
- 羅生門で下人はなぜ怒ったのでしょうか?
- 羅生門における下人の最後の行動

羅生門に現れた下人の境遇は?
芥川龍之介の「羅生門」の物語は、一人の下人が主人から暇を出され、完全に途方に暮れている場面から始まります。これは、彼が安定した職と住む場所を同時に失い、明日生きるための糧さえない極限状況に置かれたことを意味します。
舞台は平安時代の末期、度重なる災害や戦によって都は荒廃しきっていました。人々は飢饉に苦しみ、社会全体が秩序を失っていたのです。このような時代背景は、下人一人の問題ではなく、多くの人々が同様の苦境に立たされていたことを示唆しています。
彼が雨宿りのために身を寄せた羅生門は、修理もされず打ち捨てられ、死体が放置されるほどの場所でした。この荒れ果てた門の様子は、当時の社会の混乱と、下人自身の荒涼とした心象風景を映し出す鏡のような役割を果たしていると考えられます。
要するに、下人は自身の力ではどうすることもできない社会の大きなうねりの中で、生きる術を失った無力な存在として登場するのです。
下人は羅生門の下で何を考えていたのか?
羅生門の石段に腰を下ろした下人は、生きていくための二つの選択肢の間で激しく揺れ動いていました。一つは、たとえ餓死することになっても、決して悪事は働かないという道徳的な生き方です。そしてもう一つは、生き延びるために盗人になるという、道徳を捨て去る生き方でした。
当初、彼の中には「盗人になる」という選択肢を肯定する「勇気」がありませんでした。これは、彼が本来持っていた倫理観や良識が、悪の道へ進むことを強くためらわせていたからです。彼は何度も同じ考えを巡らせながらも、なかなか結論を出せずにいます。
この葛藤は、極限状況に置かれた人間が、自身の尊厳と生存本能との間でいかに苦悩するかを鮮明に描き出しています。雨が降りしきる羅生門の下という閉鎖的な空間で、彼の内面では激しい嵐が吹き荒れていたのです。
以上の点を踏まえると、羅生門の下で彼は、人間としての最後の理性を保とうとしながらも、生きるという根源的な欲求から逃れられないという、絶望的なジレンマに陥っていたことが分かります。
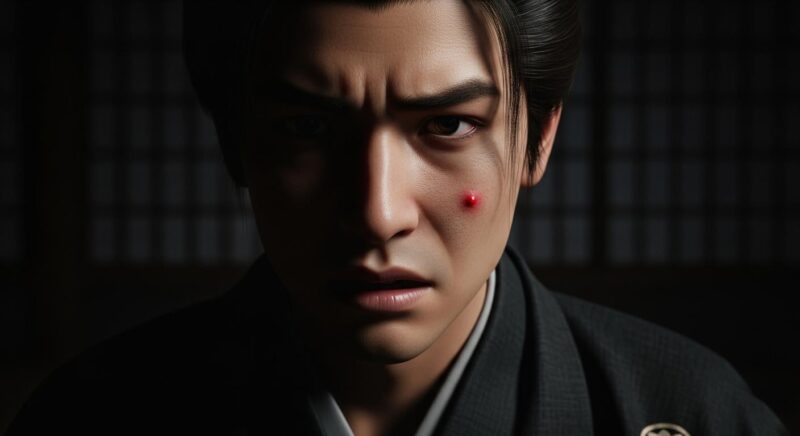
羅生門のにきびは何を象徴しているのでしょうか?
物語の中で、下人の右の頬にできた「大きなにきび」について言及されています。これは単なる身体的な特徴ではなく、作品のテーマを暗示する象徴的な装置として機能していると考えられます。
一般的に、にきびは思春期や若さの象徴とされますが、この物語においては複数の解釈が可能です。
解釈1:内面的な葛藤の表出
一つは、下人の内面で渦巻く葛藤や、餓死か盗人かという不健全な考えが、身体的な徴候として現れたとする解釈です。解決できない悩みやストレスが、化膿したにきびとして彼の外面に表れているのかもしれません。
解釈2:社会の病理の象徴
もう一つの解釈として、このにきびが、荒廃した平安京という社会全体の「病」を象徴しているという見方もできます。社会の秩序が乱れ、人々が道徳を失っていく状況が、下人という一個人の身体を通して表現されているのです。
解釈3:醜さへの伏線
さらに、これから彼が犯すことになる「悪」や、人間の持つエゴイズムという内面的な醜さへの伏線とも捉えられます。老婆の醜い行いを見て、彼自身の内にもあった醜さが呼び覚まされるきっかけとなるのです。
これらのことから、頬のにきびは、下人個人の問題と社会全体の病理、そして物語の根幹をなす人間のエゴイズムを結びつける、多層的な意味を持つ象徴だと言えます。
羅生門で下人が失望したのはなぜ?
下人が羅生門の上で老婆の行為を目撃したとき、彼の心を満たしたのは、恐怖や嫌悪感を通り越した深い「失望」でした。彼が失望したのは、死体から髪を抜くという老婆の行為そのもの以上に、極限状況における人間の浅ましいエゴイズムに対してです。
それまでの下人は、たとえ自分が餓死しようとも、悪事は働くべきではないという倫理観をかろうじて保っていました。彼の中には、人間として守るべき一線というものがあったのです。しかし、老婆の行為は、彼の信じていた人間性の最低限の尊厳すらも打ち砕くものでした。
老婆は死者の髪を抜き、それをかつらにして売ることで生き延びようとしていました。死者への冒涜も厭わないその姿は、生きるためには手段を選ばないという、赤裸々な利己主義の表れです。
この光景を目の当たりにした下人は、自分がこれまで守ろうとしてきた道徳や正義がいかに脆く、無価値なものであるかを痛感させられます。したがって、彼の失望は、老婆個人に向けられたものというよりは、人間の本性そのものに向けられた、根源的な絶望であったと考えられます。
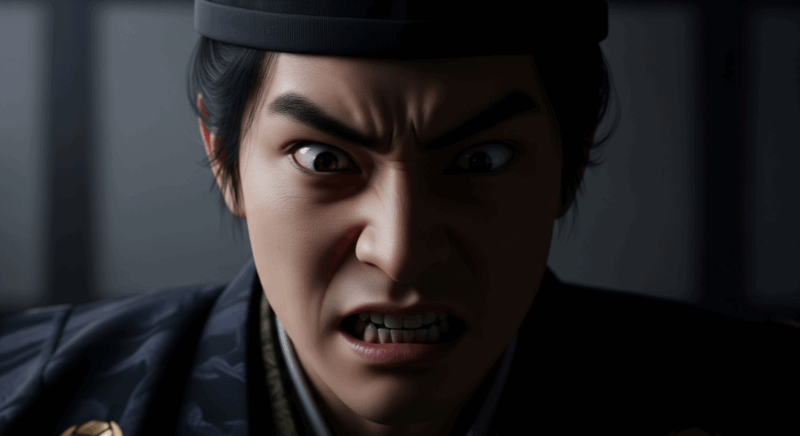
羅生門で下人はなぜ怒ったのでしょうか?
老婆の弁明を聞いた後、下人の心には「はげしい憎悪」に似た怒りが込み上げてきました。この怒りの本質を理解することが、彼の行動原理を解き明かす鍵となります。
老婆は、自分の行為を「こうしなければ餓死するのだから、仕方がない」と正当化します。さらに、この死体の女も生前は蛇の干物を魚だと偽って売っていたのだから、自分が髪を抜くことも許されるはずだと主張しました。この「生きるためには悪も許される」という論理が、下人の心に火をつけたのです。
このとき下人が感じた怒りは、正義感からくるものではありませんでした。むしろ、老婆の言葉が、自分が盗人になることをためらっていた心の壁を取り払い、悪事を働くための完璧な「言い訳」を与えてくれたことに対する、利己的な感情の高ぶりだったのです。
つまり、彼は老婆の論理を逆手に取り、「自分が生きるために老婆の着物を奪う」という行為を正当化する口実を見出したのです。彼の怒りは、道徳からの解放と、生存本能を肯定されたことへの激しい喜びが転化したものであり、彼の悪への転落を決定づける感情だったと言えるでしょう。
羅生門における下人の最後の行動
老婆の言い訳を聞き終えた下人は、態度を豹変させ、彼女に襲いかかります。そして、「では、己(おれ)もそうしなければ、餓死する体なのだ」と言い放ち、老婆の着物を剥ぎ取って闇の中へ駆け下りていきました。これが、物語における下人の最後の行動です。
この行動は、彼がそれまで葛藤していた「餓死か、盗人か」という問いに対して、明確に「盗人になる」という答えを出した瞬間を意味します。彼は、老婆が示した「生きるための悪」という論理を、そっくりそのまま自分の行動原理として採用したのです。
行動の持つ意味
- 道徳との決別: 着物を剥ぎ取るという暴力的な行為は、彼がこれまで持っていた倫理観や良識と完全に決別したことを示しています。
- エゴイズムの肯定: 他者の犠牲を顧みず、自らの生存を最優先するエゴイズムを肯定し、実践したことになります。
- 悪の連鎖: 老婆が悪事を働いて生き延びようとしたように、下人もまた悪事を働くことで生きようとします。これは、悪が悪を生むという絶望的な連鎖を象徴しています。
これらの点を踏まえると、下人の最後の行動は、単なる強盗行為ではなく、一人の人間が極限状況下で道徳を捨て、獣的な生存本能に従うことを選択した、決定的な転落の瞬間として描かれていることが分かります。
羅生門の結末と下人の行方についての多角的な考察
- 芥川龍之介の羅生門の最後の一文は?
- 羅生門の最後の一文が持つ変更理由
- 羅生門の下人の行方は誰も知らないという結末の効果
- 羅生門の下人の行方を想像するその後のストーリー
- 羅生門におけるその後の老婆の行方
- まとめ:羅生門 下人の行方 考察の総括
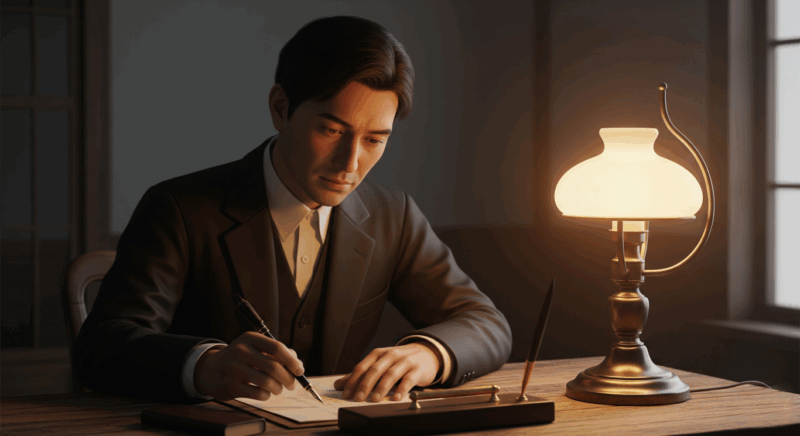
芥川龍之介の羅生門の最後の一文は?
芥川龍之介の「羅生門」は、読者に強烈な印象を残す、非常に簡潔な一文で締めくくられています。物語の最後を飾るのは、「下人の行方は、誰も知らない。」という言葉です。
この一文は、老婆の着物を剥ぎ取って夜の闇へと消えていった下人が、その後どうなったのかについて、作者が一切の説明を放棄していることを示しています。彼の運命は完全に読者の想像に委ねられており、物語は明確な結末を迎えることなく幕を閉じるのです。
この結び方は、物語の余韻を深くし、読後も「下人はどうなったのだろうか」という問いを私たちの心に長く留まらせる効果を持っています。善悪の彼岸へと踏み出してしまった人間の末路をあえて描かないことで、芥川はより普遍的な問いを投げかけていると言えるでしょう。
羅生門の最後の一文が持つ変更理由
「羅生門」の結末である「下人の行方は、誰も知らない。」という一文は、実は発表前の草稿段階では異なるものでした。この変更の理由を考察することは、作者・芥川龍之介の意図を深く理解する上で非常に有益です。
当初の草稿では、下人がその後、京で有名な盗賊になったという趣旨の記述があったとされています。もしこの結末のままであれば、物語は「一人の男が盗賊になった」という個人的な物語として完結していたでしょう。
しかし、芥川は最終的にこの具体的な結末を削除し、行方を不明とする形に書き換えました。この変更には、以下のような意図があったと考えられます。
| 項目 | 旧稿(初稿)の想定 | 決定稿 |
| 物語の焦点 | 下人という個人の運命 | 人間誰しもが持つエゴイズムという普遍性 |
| 読者への効果 | 物語の完結による納得感 | 想像の余地と、テーマについて考えさせる問いかけ |
| テーマの深化 | 個人の堕落物語 | 極限状況における人間の本質を問う普遍的な物語 |
このように、結末を変更した最大の理由は、物語のテーマを個人の堕落から、より普遍的な「人間のエゴイズム」へと昇華させるためであったと考えられます。下人の行方を「誰も知らない」とすることで、読者は「もし自分が下人の立場だったら」と考えざるを得なくなり、物語は単なる昔話ではなく、現代に生きる私たち自身の問題として立ち現れてくるのです。

羅生門の下人の行方は誰も知らないという結末の効果
前述の通り、物語の結末を下人の行方を不明とすることで、作品には多層的な効果が生まれています。この開かれた結末(オープン・エンディング)は、読者の心に深く働きかける巧みな文学的技法です。
主な効果としては、第一に、読者の想像力を刺激することが挙げられます。下人が大盗賊になったのか、それともすぐに捕まってしまったのか、あるいは罪の意識に苛まれて死んだのか。答えがないからこそ、私たちは様々な可能性を思い巡らせ、物語の世界に長く留まることになります。
第二に、物語のテーマを普遍化する効果があります。下人の末路を具体的に描かないことで、この物語は「下人」という特定の個人の話ではなく、「人間」そのものの話として立ち上がってきます。極限状況で善悪の判断が揺らぐのは、下人だけではないかもしれない、という問いを読者に突きつけるのです。
そして第三に、強い余韻を残す効果が生まれます。物語が終わった後も、羅生門の闇へと消えていく下人の後ろ姿が脳裏に焼き付き、人間のエゴイズムや「生きること」の意味について、深く考えさせられることになります。これらの効果によって、「羅生門」は時代を超えて読み継がれる不朽の名作となっているのです。
羅生門の下人の行方を想像するその後のストーリー
「下人の行方は、誰も知らない。」という結末は、私たち読者に、その後のストーリーを自由に想像する余地を与えてくれます。彼の運命には、いくつかの可能性が考えられるでしょう。
一つは、彼が盗人として生きる道を選び、京の都で悪事を重ねていくというストーリーです。一度悪に手を染めた彼は、ためらいを捨て、生きるために略奪を繰り返す冷酷な人間になったかもしれません。もしかしたら、草稿にあったように、名うての盗賊として知られる存在になった可能性もあります。
逆に、全く異なるストーリーも想像できます。老婆から奪った着物で一時的に飢えをしのいだものの、すぐに罪の意識に苛まれ、結局は餓死してしまったという悲劇的な結末です。あるいは、最初の盗みがうまくいかず、すぐに捕吏に捕らえられ、厳しい罰を受けたという展開も考えられます。
また、彼が盗みを続けたとしても、心の中に常に「にきび」のような良心の呵責を抱え続け、決して満たされることのないまま生きたという、精神的な地獄を描くことも可能です。このように、下人のその後のストーリーは一つではなく、読者の数だけ存在すると言えるでしょう。

羅生門におけるその後の老婆の行方
物語の焦点は下人の行方に当てられがちですが、彼によって着物を奪われた老婆がその後どうなったのかも、考察の対象となります。下人と同様に、彼女の行方もまた、羅生門の闇の中に消えています。
老婆は、生きるための唯一の手段であった「死人の髪を抜いてかつらにする」という仕事道具と、寒さをしのぐための着物の両方を失いました。当時の荒廃した社会状況を考えれば、彼女がその後、生き延びられた可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
下人が自らの生存のために老婆を踏みつけにしたように、老婆もまた誰かの犠牲の上に生きようとしていました。この物語では、誰もが加害者であり、同時に被害者でもあるという、救いのない悪の連鎖が描かれています。
したがって、老婆のその後の行方を想像することは、下人が犯した罪の重さと、物語全体を覆う絶望的な世界観をより深く理解することに繋がります。彼女の末路は、下人の選択がもたらした直接的な結果であり、彼の背負った業の象徴とも考えられるのです。
まとめ:羅生門 下人の行方 考察の総括
- 下人は主人に暇を出され生きる術を失った境遇にあった
- 当初は盗人になることをためらう倫理観を持っていた
- 頬のにきびは内面の葛藤や社会の病理を象徴する
- 老婆の行為を目撃し人間のエゴイズムに深く失望した
- 老婆の言い訳が下人が悪事を働くための口実となった
- 下人の怒りは正義感ではなく自己中心的な感情の高ぶりだった
- 最後の行動は道徳との決別とエゴイズムの肯定を意味する
- 結末の一文は「下人の行方は、誰も知らない。」である
- この結末は作者によって意図的に変更されたものだった
- 結末の変更は物語のテーマを普遍化する狙いがあった
- 行方を不明にすることで読者の想像力をかき立てる効果がある
- 下人のその後は盗賊になった、捕まったなど複数の想像が可能
- 着物を奪われた老婆の末路もまた過酷であったと考えられる
- 物語は誰もが加害者にも被害者にもなりうる悪の連鎖を描く
- 羅生門は極限状況における人間の本質を問う普遍的な作品である